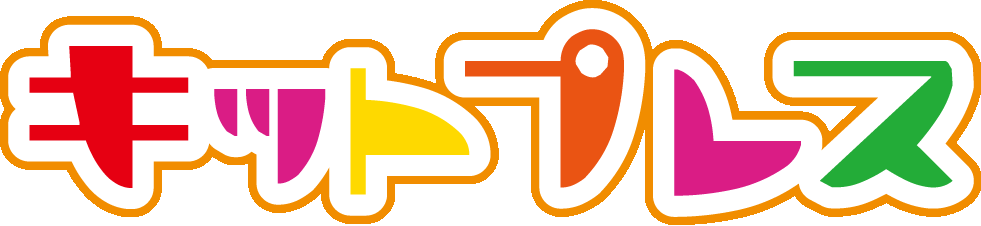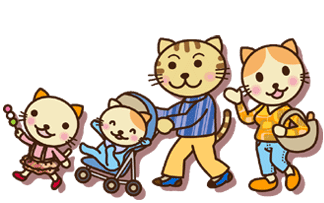ヴィーガンやったらココ!って、言ってもらえる店に育てたい

アレコレ考える前にまず走り出す!何が起きるかハラハラ、ワクワク… 1年前「Vegan caffe Nana」をオープンさせた時もやっぱりそうだった。
「いつもイケるやろ、なんとかなるやろって取りあえず動き出すんです。後からどうしよってなる事もいっぱいあるんだけど、1つずつ乗り越えていけば大丈夫かなって(笑)」
泉州では珍しい純粋菜食の“ヴィーガン料理”に目を付けたユニークさ、そして夜中までキッチンにこもっては次々オリジナレシピを生みだすヒラメキ力。走り出してからさらにアップしていくスピードとパワーは見事なもの。
「NOって言うのがイヤなんです。無理って思ったらそれで終わり。どんな事でも取りあえず飛び込んで、そこから必死で勉強する。人生ってまたとないチャレンジだと思うから」
ヨガの楽しさを伝えたい
彼女、地元ではちょっと有名なヨガのインストラクターでもある。
阪南や泉南、岬町に15もの教室を持ち、生徒数は200人を超えるというから驚き。
「7歳のころからモダンバレエやヒップホップなんかをやっていて、ずっと体を動かすのが大好きだったんです。ヨガに出会ったのは20代後半かな?習い始めて心と体はつながってるんだとか、深い呼吸と瞑想でエネルギーを感じられることとか、本当に奥が深いんだなあってどんどん面白くなって」
だが勉強すればするほど難しくもなるし、レベルの高いポーズが増えてきたりもする。
「もっと誰でも楽しめて、体にも心にも効いてくるストレッチのようなヨガを教えたい…」
そう思った彼女は様々な種類のヨガを習い、それを組み合わせながら自分だけのヨガのカタチを作り出してきた。
「生徒さんは年配の方が多いんだけど、『ヨガ始めてから、ヒザが全然痛くなくなったわ』とか『ヨガって気持ちいい』って言ってもらえる時が最高にうれしい。ヨガって、心と体の声に耳をかたむけることなんです。ここを伸ばしたら気持ちいいんやとか、体が歪んでたから痛かったんやなとか。自分の体を知ることが大事なんですよね」
たった2人の生徒から始めたレッスン、それが口コミで広まり今では公民館、文化ホール、スポーツクラブ…と走り回る毎日。
「阪南ではうちのヨガ教室も知られるようになってきたし、任せられるお弟子さんも育ってきた。じゃあ次は何しよかなって思った時ひらめいたのが、『お店出したい!』やったんです」
「子どもの頃から、なぜか食べ物のお店したいって思ってたんですよね。人が集まる場所を作りたいっていうか。いつかやれたらいいなと思って、子育てしながらお寿司屋さんでバイトして、調理師免許もとってあったんです」
人生はチャレンジ、ジッとしてられない彼女は次の夢に向けて動きだす。
体に優しい料理を食べてもらいたい
「ちょうどお店を探しだした頃に、今のこのログハウスに一目ボレ。そこからどんなコンセプトでやるのかとか、内装工事やら準備やらバタバタッと決まって。もう昔からこんな感じ、先に決めちゃってから考える(笑)」
思いついて2ヶ月後にはもうオープンしていたというから、持ち前の“なんとかなる”精神が生むスピード感がスゴイ。
フードから衣類まで、世はまさにオーガニックブーム。健康と安全をお金で買うのは、もう当り前の時代になった。
とはいえ肉や魚貝、卵や乳製品までも一切使わない、ヘルシーの究極ともいえる“ヴィーガン”を選んだのは何故なのか――
「ずっとヨガをやってきて、体が一番喜ぶ食材ってなんだろうって思ったんです。体は食べたものからできている、だったら胃腸を休ませてあげる、体に優しい料理を食べてもらいたいと思って」
バターやハチミツはもちろん、調味料まで動物性のものは一切使えないとなると、なかなかメニュー作りも難しそう。
「でも色々試して新しいレシピを創るの、大好きなんです。例えばパンを焼いたら、これに合うバターが欲しい。じゃあココナッツオイルで作れないかな、メープルシロップも入れたら美味しいん違うかなとか。失敗もメッチャします、でも料理を考えてる時間てすっごく楽しい!」
カシューナッツと豆乳、チャナダル豆と野菜など3種のカレーは大人気。和風に中華にデザートまで、彼女の工夫が詰まったメニューはどれもシッカリした旨みがあって、遠くから訪れるファンも多い。
ヨガのインストラクターにお店のオーナー、そしてシェフ…もう目が回るほど大忙しなはず。
「朝お店で仕込みして、昼はヨガ教室、夕方飛んで帰ってまた店で料理作って…みたいな毎日。よくそんなに動いてられるねって言われます(笑)でも娘が店長やってくれてるし、1年経ってお金のこととかお客さんの流れとか、色んな事がわかってきた。大変だけど『さあ、ここから!』っていう気持ち。ヴィーガンやったらうちの店やって、みんなに思ってもらえるようなそんなカフェに育てていきたいんです」
2015/8/28 取材・文/花井奈穂子 写真/ 小田原大輔