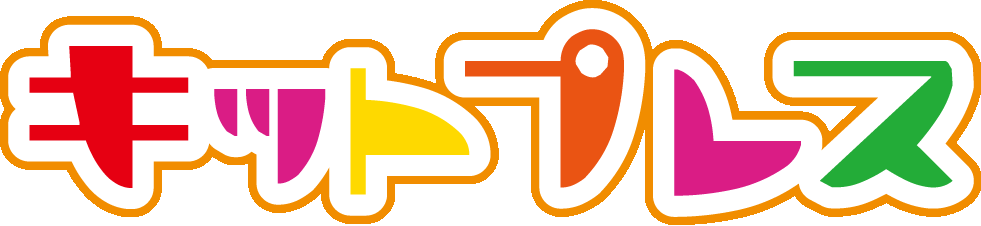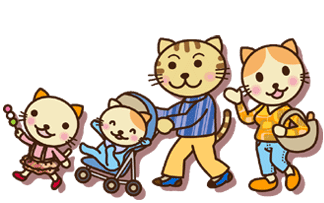ギターは言葉よりもずっとうまく、自分を伝えてくれる

「コレだ!」という直感を信じて走ってきた。
見た瞬間「ここしかない!」とひらめいたニューヨーク。ツテがあるわけでもないその場所にいきなり飛び込み、「ギタリスト」という夢を追いかけた若き日々――しかも自分で師匠を探しては弟子入りし、腕を磨くという独特のやり方で“夢への距離”を詰めていった。
そこで出会った恩師、音楽、経験…そのすべてが“今”につながる。
「僕にとってギターは、自己表現をするための最高の手段。ギター1本あれば、国も言葉も、人種だってアッという間に飛び越えられる。音楽ってそういうものですよね。海外で初めて会った人と、いきなりセッションが始まって友だちになったり…。ギターは僕にとって、きっと言葉よりずっとうまく自分を伝えられるアイテムなんだと思います」
ギタリスト、マイク・スターン氏との出会い
中学の入学祝いにもらった一本のギター、それが彼の人生を決めた。
「部屋はもうギターやら音響楽器でいっぱい!今振り返ってみてわかるんですけど、完全にハマってました。高校の頃ギターやるヤツって、いっぱいいるじゃないですか。ライブやったり、バンド組んだり。けどみんな受験や就職のことはちゃんと考えてる。『プロになる!ギターで食ってく!』みたいに本気モードだったのは、気がつけば僕らだけやったんですよ(笑)」
とはいうものの、「やっぱり仕事はせなアカンかなと」考え直し、高校を出るとサラリーマンとして働きだす。だが、どうしてもぬぐいきれないギターへの思い、日々への違和感…。
「すごいしんどかった。ムリしてたんです。仕事がイヤなわけじゃないけど、これは自分がやりたい事とは違うって」
結局3年半で退職、とき放たれた鳥のように彼の心は音楽の本場、アメリカへと向かう。
「ロサンジェルス、ラスベガス、ボストン…三ヶ月間あちこち回ったんですけど、たまたまロスで知り合った友だちに誘われて、ニューヨークに行ったんです。その時『ワッ、ここがイイ!ここに絶対住もう!』って稲妻に打たれたみたいになって。とてつもなく刺激的で、街の持ってる空気感がたまらなく魅力的だった」
思い立ったら、足を止めているヒマなんかない!日本に戻るや、資金づくりのためにバイトをスタート。1年でお金を貯めると、そのままニューヨークに飛んだのだ。
ジャパニーズレストランで働きながら、英会話とギターの練習に明け暮れる日々。さぞストイックな毎日…と思いきや「当時はチップだけでかなりの額がもらえて…不自由なく暮らせるくらいは稼げたんですよ。それに奇跡のように、素敵な出会いがいくつもあった。ギターの恩師、帰国するまでずっと働かせてもらったレストランのオーナー、たくさんの仲間…まるで申し合わせていたように、抜群のタイミングで出会うんです。人に恵まれたから9年間も暮らせたし、今の僕があるんだと思ってます」
なかでも6回もグラミー賞候補になった、世界的なギタリスト、マイク・スターン氏との出会いは鮮烈だった。
「どうしても教えてほしくて、頼みこんだんですが、その場で断られたんです。数回目でやっとOKが出たんだけど、これ彼がいつも相手のヤル気を試すためにやってる“リトマス試験紙”みたいなものだったんです」
「彼は僕をすっごく変えてくれました。一日のうちできる限りの時間をすべて練習にあてるという、音楽に対する厳しい姿勢。それとは反対に人に対して、とっても穏やかで優しい人柄…彼にめぐり会ったことで、人間的にとても優しくなれたと思う」
社会に貢献できる幸せ
一目ボレしたニューヨークの街でジャズを学び、ギターの腕を磨き、結婚もした彼だったが、暮らせば暮らすほどアメリカ人との感覚の違い、ギャップにとまどうようになる。
「例えば健康に対する感覚。好きなものを好きなだけ食べて、栄養はサプリでとればいいとか、食を大事にする僕ら日本人とは考え方が違うんですよね。そんなズレがあちこちに見え出して、もうついていかれへんなと思ってしまったんです」
ちょうど子どもが生まれたこともあって、思い切って帰国することを決意。青春そのものだったアメリカに別れをつげることにしたのだ。
戻ってからは「Passion and actions」ほか3枚のCDをリリースするほか、幅広い人脈を活かして様々なプレーヤーと共演。女優松坂慶子の夫でもあるギタリスト、HARU高内氏とも毎年コンサートを開く仲だ。
さらに大阪市内、三重県など三ヶ所に自らが主宰する「イチギター音楽総合スクール」を開き、15歳から80歳までの生徒にギターの魅力を伝える。
だが一方で彼のなかに、音楽や英語を通じて社会に貢献したい、力になりたいという、今までとは違うアツい思いも生まれはじめた。
「例えばもし依頼が来るなら、校歌を作りたいなと思ってるんです。みんなが歌ってくれて、それが次世代に残っていく。自己表現も大事だけど、誰かが喜んでくれたり、地元の力になれたり…それって幸せなことだなって」
本場でつちかった英語力を活かし、地元狭山の公民館で「即戦力英会話」の講座を開いたり、自らが習う拳法「達磨拳」道場に留学生が訪れた時には、通訳を買ってでたりと、ボランティアにも力を注ぐ。
そしてもうひとつ、成し遂げたいものがある。
「自分にしかできないギター音楽のスタイル、っていうか自分がいなくなっても受け継がれていく何かを残したい。時代とともに変わってしまうものではなく、僕流のスタイルを弟子やみんなに継いでいってもらえるように頑張りたいなと思ってます。そしていつかまた、もう一度海外に出て行って演奏できればいいなあ」
<2014/4/15 取材・文/花井奈穂子 写真/ 小田原大輔>