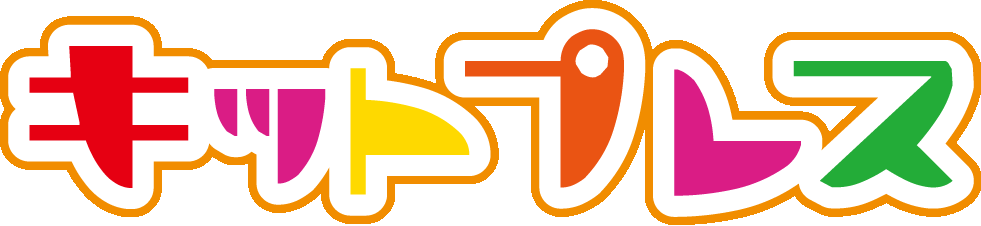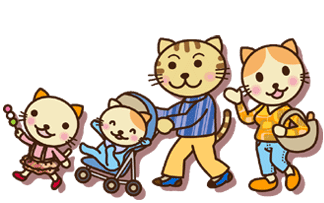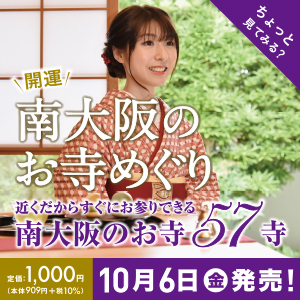私にしかできない、新しい紙芝居のカタチを創りたい

いろんな意味で“規格外”な人である。
「やってみたい!」と思った瞬間走り出す、その爆発力とマイペース感! アイデアが次々あふれて、自分でもその広がりを「コントロールできなくなってしまう」というのびやかさ。小さなワクにおさまりきれない…それこそが彼女の魅力だ。
「いつも楽しんでいたい。好きじゃない事をして生きるのは、どうも向いてないんです」
ひたすら心がときめく方へ、ワクワクする方へ…走り続けてたどり着いたのは紙芝居という、ちょっとレトロな世界。ここでまたどんな“果林ワールド”を展開するのか…
あたり前じゃないからオモシロい、はみ出しぶりがまたイイのだ。
キライだった声を武器に
紙芝居に魅かれた原点――それは、妹たちに本を読んで聞かせるのが大好きだった幼い頃にある。
「これ面白い!」となったら、誰かに教えずにはいられない。
キャラクターをたくみに演じ分けて本を読み聞かせ、みんなが笑ってくれるのを見るのが、また幸せ。
TVで「ちびまる子ちゃん」を見ると、さっそく友だちにお気に入りのシーンを再現して見せては笑いをとる…そんな誰かに語ったり演じたりするのが好きでたまらない少女だった。
だが、低音でよく響く自分の声は大嫌い。
「なんでこんな可愛くない声なんやろって、小さい頃からコンプレックスやったんです」
でもこの声があるから、人にはできない役も演じられる。迫力あるシーンも再現できる……そう気づいた時「この声も結構いいじゃん!って思えるようになった。イヤでしょうがなかった低い声が、見方を変えれば個性になる。声優の世界やったら、コンプレックスが逆に武器になるんちゃうかなって」
そう確信するや、迷わず声優の養成所へ。
だが3年目、ふと友だちに誘われて出かけた小劇場で、思いもかけなかった世界に出会ってしまう。
「もう体に衝撃が走ったんです。狭い劇場やから、役者の汗まで飛んでくる、こんなアツくてエキサイティングな世界があったんや!ウワァ、やりたい!ってなってしまって(笑)」
ビビッときたら、走り出す。
授業に何かしっくりこないものを感じ出していたこともあって、すっぱり養成所を辞め、演劇の世界に飛び込んでしまったのだ。
そこからは小劇場での活動を中心に、一気に演劇の面白さにのめりこむ。
自分にしか登れない、人生の山を極めたい
だがその一方で、生活費を稼ぐために始めたアルバイト先で、ちょっとした心の変化が起きていた。
当時道頓堀に、鳴り物入りでスタートしたフードテーマパーク「極楽商店街」。大正から昭和のレトロな街並みを再現した館内には、50を超える飲食店が並び、お笑いやライブ、寄席……といったさまざまなパフォーマンスが繰り広げられていた。
「業務の仕事で入ったんですけど、“やってみいひん?”って誘われるまま、お客さんの前に立ち始めて。そこで紙芝居をやらせてもらったんです。それがメチャメチャ楽しくなって!」
自己表現の場として飛び込んだ演劇は、たしかに刺激的で面白い。
「でも、本当はシンドイなあって思ってた。演技の勉強はもちろん、作業とか全部みんなで作り上げていかなきゃならない。だんだん私生活との両立ができなくなり、疲れてしまったんです」
それにくらべて紙芝居はひとりでできる。
彼女の語りに耳をすませ目を輝かす子、ツッコミを入れてくる子…その場でビンビン感性が伝わってくる面白さ。
「ああ、懐かしいなあって。本を読み聞かせるのが好きだった、子どもの頃を思い出したんです。私ってやっぱりこういうことが好きやったんやってワクワクしてきて」
こうなると、心が傾いていくのを止められない。
当初は半年で200万人を動員した「極楽商店街」も、結局たった4年で幕を降ろすことになるが「最後の日、スタッフに『あひるの王様』っていう紙芝居をプレゼントされたんです、どこかでまたやってねって。こうなったら絶対やるぞって(笑)」
一昨年からは役者業も辞め、泉州のイベントを中心に紙芝居師として活動中。
だが、やっぱりここに安住してしまう彼女ではない。いつだって心のときめく方へ、ワクワクする方へ……。
「私にしかできない、新しい紙芝居のカタチが創れればいいなと。もちろんオリジナルのお話をもっと描いていきたいし、紙というワクにとらわれなくてもいい。いつかパフォーマーとして認められたいっていうのが夢なんです」
声優を目指したことも役者修業も、気が付けばすべてが彼女の大きな糧となって、今につながる。
「なんかアルピニストの気分。自分にしか登れない、人生の山を極めたいって今、すごく思います」
2012/9/1 取材・文/花井奈穂子 写真/ 小田原大輔