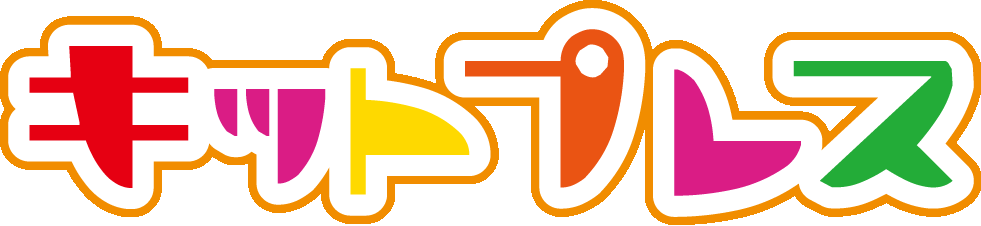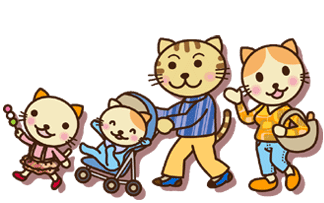版画は生きることそのもの。
私らしいオリジナリティをずっと追い求めていきたい

人生に“使命”というものがあったとして、それを全力でまっとうできる人間がどれほどいるだろう。
生活や毎日の雑務に追われ、孤独にひるみ、結局あたり前の幸せとひきかえに、人は一番大切な夢を失っていく。
Appleの創始者として名を成した、あのジョブズ氏もいっている。「君たちの時間は限られている。もっとも大事なのは、心の声、直感に従う勇気を持つことだ。それ以外のことはすべて二の次でいい」
その“心の声”が決めた道を、揺らぐことなく歩き続けているのがこの人だ。
「私のなかで版画は“生きること”そのものなんです。本を読むこと、人と会うこと、景色を見ることもすべて作品を創るためといっても過言じゃない。なんか版画のことばかり思っていて、普通の人がフツーにやってることが出来ない、バランスが悪いの(笑)」
自分が持って生まれた“使命”、他の誰にも出来ない何か……それを追い続けることは、とてもシンプルで、とても難しい。だが、それを成せる人だけが、新しい何かを生みだし後世に感動を伝えていく。
電車に乗れない
生まれた時から、チンチン電車が走る音を聞いて育った。
実家は線路のそばにある、当時日本でたったひとつの小さな「自転車補助輪専門工場」。
幼い頃の父との思い出は、彼女が綴った絵本「こどもほじょりん製作所(講談社)」に、ユーモアいっぱいに描かれている。
9歳になってもまだ補助輪をはずせない“おっとりすまこ”と、彼女を特訓するせっかちなプリプリとうちゃん……「ええかげんにせんかっ!いつまでかかってるんじゃ!」「もうちょっと、はよこがんかあ!」――ペースの合わない父に振り回されながらも、ついに自転車にひとりで乗れるようになるまでを、温かく描いている。
「父はむちゃくちゃ頑固で、昔かたぎのうるさいオッチャン(笑)。でも正直に生きてる、ほんとに愛らしい人でした…」
そんな庶民的な町でのんびり育った彼女が、大阪芸大を目指したのは「なんか楽しそうなとこに行きたかった」から。「それまで女子高だったので、面白くなくて……男子もいるし楽しそうかなあって」 彼女らしいフワフワとした理由だった。
「もともと木版画家の棟方志功が好きやったんです。それで版画に行ったんですけど、勉強するうちに銅版画でしか現せないチクチクした“線”の魅力にハマってしまって……」
なんとなく踏み出したはずのアートの世界で、彼女は“銅版画”という自分を表現できる最大のツールを見つけたのだ。
4年後大学を卒業、はれて中学校の美術教師になったものの、なんとも意外なところでつまずく。
「毎朝同じ電車に乗ることが、シンドくてシンドくて……。毎日電車に乗って規則正しく仕事に行く……そんな大変なこと私にはムリ!って気づいたんです。教えることは楽しかったんやけど、私はこういう普通の生活に向いてないんやと、諦めました(笑)」
結局1年で仕事を辞め、大阪芸大付属浪速短大で副手をしながら、晴れてフリーになり創作の道を歩き出すことになる。
作家、村上龍氏との出会い
そんなある日、高校時代から大ファンだった作家、村上龍氏の講演会が大阪で開かれるという記事を見て、「会ってみたい」と駆けつける。
サインをしてもらいワクワクドキドキ、思わず持っていた自分の版画を氏に手渡した。だが急いでいた彼は、作品を大阪空港に忘れて帰ってしまう。
不運なアクシデント。
ところが、なんとそれが彼女にとって大きな転機となるから人生は面白い。
しばらくしてかかってきた電話をとると、なんとあの村上氏! 作品を失くしたことを詫びようと、わざわざ連絡してくれたのだ。
「大好きだったから、もうビックリ!ラジオで聴いてた、もうあのままの村上龍さんの声なんです。それからしばらくしてからかな、本のお仕事をいただいたのは……」チャンスはどこに転がっているかわからないのだ。
銅版画ならではの硬質でカリカリとしたラインと、その上からパステルで彩色することで生まれる、まるで夢を見ているようなやわらかで幻想的な世界。作品に惚れ込んだ村上は以後、自身の作品に何度も彼女の版画を用いる。
「69 sixty nine」「すべての男は消耗品である」「ラッフルズ ホテル」……あの、一度見たら忘れられない独特の装画は、こんな出会いから生まれたのだ。
最近では、国内外の文豪の短編を集めた「百年文庫(ポプラ社)」に、力のすべてを注ぎ込んだ。自身、初めて手掛ける木版画の仕事だった。
なにせ100巻にもおよぶ作品のすべてを読み、下絵を描き、彫り、刷る……「電車でも、ベッドのなかでも、読んで読んで読みまくり。そして最高に忙しい時は2日に1点仕上げていくという、人間業ではないペースで寝ても覚めても彫り続けました。しまいには『鬼彫り』『鬼刷りのすまこ』と呼ばれて…もう、負けるもんかって(笑)」
おっとりした彼女のどこに、そんなエネルギーと燃えたぎるような情熱が潜んでいるのか……。一度制作にかかると、生活のすべてが創作に注がれる。何にも惑わされず、本質だけを見つめる才能は彼女ならではのものだ。
「私、熱血な人が好きやねん。こう見えて私はやるとなったら、徹底的にやる。本気で仕事をする。だから一緒に熱くなってくれる人と仕事したいんです」
有名になりたいとも、裕福に暮らしたいとも思わない。
想いはただ作品のことだけだ。
「最近はずっと花をモチーフに描いているんですけど、もあっとした空気感というか非現実の世界というか……私にしかないオリジナリティをこれからも極めていきたい。一目見て『あ、これすまこさんの絵や』って、いってもらえる・・・それがうれしいんです」
2012/6/14 取材・文/花井奈穂子 写真/ 小田原大輔