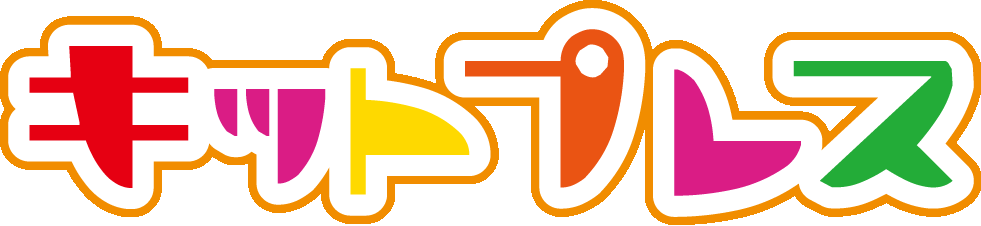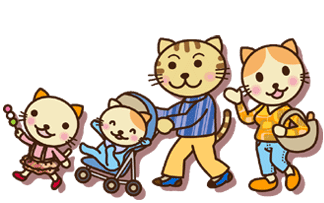人生は自分にしかない“オリジナル”を見つける旅

機織りがしたいとなれば、床と鴨居に釘をうってタコ糸をかけ、幻想的な布を織りあげてしまう。
メニエール病にかかれば、なんと目まいの症状ををそのまま縫い上げて「ウズマキアート」にしてしまう。
人生にムダなものは何もない、彼女にとって失敗やつまずきも、短所も全部が神様からのプレゼント。フツフツとわき上がるエネルギーとアイデアで、すべてをアートに変えてしまうのだ。
「短所は活かすためにあるの。それは自分にしかないオリジナルなんやから、大事にせんとあかんのよ……」
誰に技術や手法を教わったわけでなく、表現したいという思いに突き動かされて、作品を創り続けるいわば“アウトサイダー”。
だが常識にとらわれないからこその、あふれ出す感性はまさにオンリーワン。その圧倒的な迫力のうずに、私たちは引きずり込まれるのだ。
布アーティスト・米倉健史氏との出会い
原点は、いつも祖母と一緒だった幼い頃にある。
「祖母がいつもお裁縫をしてたんですね。だから私もそのそばで、ひとり遊びといえば針と糸を使ってた。3歳のころには、もう勝手に布でぬいぐるみを作ってたり……。あの時間が今の私を生み出してくれたのかも」
それきり眠っていた本能を再び目覚めさせたのは、結婚して暮らすことになった山口県・下関での“孤独”な時間だった。
「知らない土地で、一日中たったひとり。寂しくてどうしようもない時間を埋めてくれたのが、モノづくりだったんです。」
手はじめに作ったのが、わが子のためのベビー布団。
「ワタを入れて表と裏縫ったらできるんちゃうかなと。で、やってみたらできるやんって(笑) 何かを手作りしてる時間がもう楽しくて、心が安定するんですね。孤独も悪くない、創造を生みだすために必要なんやなと」
そして男の子ふたりの子育てに追われながら、次に転勤になったのは広島。
いよいよここから、出口を探していたかのような彼女のエネルギーは、一気に動き出す。まるで彼女自身が磁石になったかのように、いつも次の扉を開けようとするタイミングで大事な人が現れ、そして新しい素材にめぐり会うことが続いていったのだ。
そのひとつが憧れていた布アーティスト、米倉健史氏との出会いだ。
自分で染めた布で、風景画を描くようなやわらかいパッチワークを作る彼の作風は、当時かなり異端で画期的なもの。それまでの幾何学的なパッチワークのイメージをくつがえすものだった。
矢もたてもたまらずアトリエを訪ねた彼女に、「真似するだけじゃなくて、自分で布を染めて、オリジナルの作品を創ったら?」と彼はアドバイスをくれた。
さっそく材料を買いに走り、染めてみると「オモシロい!」
それからというもの、自分だけの色を探して「毎日、気が狂ったように染めまくってました」
アートは生きることそのもの
染めたら今度は織りたくなる。
床と鴨居に糸をかけて織ったのは、新聞配達のアルバイトの途中で見た、夜から朝へ変わる瞬間の、うっとりするようなパープルの空。
さらには自転車の車輪に巻きつけて織ったり、横糸をナナメに通して織る名付けて「風織り」……と次から次へとユニークな作品を生み出していく。
「素人やからこその発想なんです。何もわからんから、自由にやりたいことを全部やってみる。そしたら何故か面白いモノができてるんです(笑)」
そして12年前、この堺に戻ってき彼女に、また新しい出会いが待っていた。
検査のため、たまたま訪れた「赤井マタニティクリニック」。その時持っていた手作りの袋に、院長が「素敵ね」と声をかけてきたことから、病院のディスプレーを手がけることになったのだ。
以来12年間、クリニックの玄関は彼女の個展さながら。フェルト、毛糸、流木・・・さまざまな素材を、独特の感性で組み合わせたビビッドな作品は、1メートル四方にも及ぶビッグなものがほとんど。毎月変わる彼女のアートを、楽しみにしているプレママも多い。
「私にとってアートは生きることそのもの。人生は自分にしかないものを見つける旅やと思うねん。ダメなとこがあっても、それもひっくるめて大切な個性」
そう、人は誰もオンリーワン、自分にしかできない何かがあるはず……それを伝えたくて作品を創り続ける。
「今の若いママたちはイジメ世代に育ってるのよね。だから目立つことや自分を出すことをとっても恐れてるし、孤独やと思うの。だからモノを作る時くらい、思い切り楽しく自己表現してほしい。自分にしかないオリジナリティを大切にしてほしい。その思いをこめて今、市民講座のお手伝いをさせてもらってるんです」
2012/4/26 取材・文/花井奈穂子 写真/ 小田原大輔