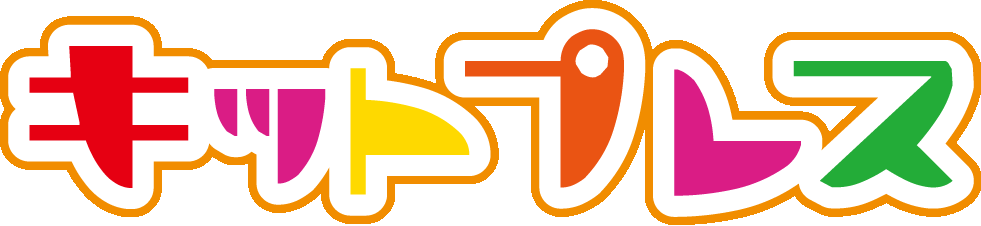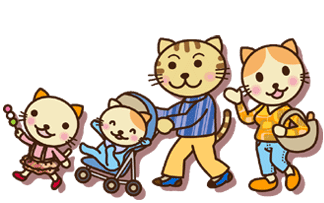両手を失くしたからこそ今、絵が描ける。生きるって楽しいんだよと伝えたい

人生とは不思議なものだ。
たったひとつの出会いが、すべてを変えてしまうことだってある。
彼もまた大石順教尼というひとりの女性と出会ったことで、思いもよらぬ人生を歩きだすことになった。
「もし私に両手があったら、絵を描くことはなかった…乗り越えてみれば、失ったものよりも得たことの方がずっと大きくて素晴らしい。それを教えてくれたのが先生なんです」
人生はいつだって平等ではない。障害を負うということはそれだけで、偏見や不都合に満ちている。だがそれでも「絶望があったからこそ、今の人生がある」と笑える彼には「この世で起こるすべてには意味がある」ことを納得させてくれる、静かな強さが漂う。
人生の師との出会い
それは一瞬のことだった。小学三年生の春休み、家業である製材工場を手伝っていたその時事故は起きた。両手を失うというあまりにも大きい絶望と先の見えない不安……。
「今まで食べるとか着るとか普通にしていたことが何もできない。あれもできない、これも無理…人からは指をさされ、からかわれる。いじめにも合う…もう死にたい、生きていてもしょうがないと何度思ったか。いつか誰にも会いたくなくて引きこもりになってしまったんですね」
生きる意味を見失っていた中学2年生の時、たまたま近所の人に紹介されて訪ねたのが、日本のヘレンケラーともいわれる尼僧、大石順教尼だった。
自身も養父に両腕を斬りおとされるという絶望を背負いながら、「嘆かず悔やまず生きる」ことを説き、京都山科の「仏光院」で障害や心の悩みを持った人たちを弟子にとり人生の道を教え続けた順教尼。彼女に出会ったことが彼の人生すべてを変えたといってもいい。
「弟子になりたいなら三つの条件があるといわれました。一つは堺から一人で通ってきなさいということ。そのためには、誰かに頼んで切符を買ってもらうしかない。片道で5回乗り換える間には、「いいよ!」といってくれる親切な人ばかりじゃない、甘えるなと怒られたり、からかう人も。でもそれはみんな社会を教えてくれる先生やと思いなさいというのが二つめの条件。そして絵を描きなさいというのが最後の条件やったんです。」
絵を描くといっても足で描くしかないと思っていた彼に、彼女は口で描くことを教える。
「絵は床の間に飾られるもの。無理なら仕方がないけれど、口で描けるのならそうしなさい。見てないところで真心を尽くさないかん!と」
ワラにもすがる思いだった彼は、ひたすら口に筆をくわえて俳画を描きはじめる。「苦しいし、歯が痛くてご飯も食べられない…でもやっと一枚絵ができた時、ああなんて楽しいやろって思えたんです。今まであれもこれも出来ないことばかりだった自分にも、絵が描けるんだ…って」
命をかけて絵を描きたい
それからというもの、「何もできない」自分から、「あれもしたい、これもしたい!」というポジティブな生き方に変わっていく。水泳にスキー、サイクリング…なんにでもチャレンジしては、ひとつずつ不可能だと思いこんでいたことが可能に変わっていく。「できない事としないことは違うんだよ」 いつもそう順教尼がいっていたように…。
2年後堺市展に入選、翌年には奨励賞も受賞。高校卒業後は日本画にも挑戦し、その繊細さ、何度となく色を重ねて生まれるたおやかな美しさに心を奪われ、画家としての道を歩こうと決心することに。
結局、運命の出会いから2年で順教尼は亡くなり、彼は最後の弟子となった。
「思えば本当に器の大きい、すごい人でした。先生は今度生まれてくるなら、また両手がない人生がいいとおっしゃったんです。手がないままやりのこしたことをやりたいと…。私も障害を負ったからこそ、今充実した日々がある――不幸と幸せは紙一重、すべては心の持ち方なんだよと、先生に教えてもらったとおりなんですね」
そして彼にとって多分障害を負ったからこそ出会えた、運命の人がもうひとりいる。妻の弥生さんだ。
「彼は私とは全然違うひと。とにかく諦めるってことがないんです。これでダメだったらこうしよう、それでもアカンかったらああしてみよう…ってとことん工夫して挑戦する。きっと大変なことも多いはずやのに、こんなにさりげなくキラキラ輝いて生きてる。私にとって彼は“尊敬”っていう言葉そのものなんです」
60歳を節目に、初めての作品集「ふりかえってみれば…」(風媒社)も出版したばかり。だが利益はすべて東日本大震災の義援金にあてるという。
「いつも仲間にささえられてばかりで、私にも何かできることはないかと思ってました。どんなに苦しくても立ち向かっていけば、いつか生きるって楽しいと思える日が来るよって思ってもらえたら…」
そして現在は、彼と順教尼の生き様に感銘を受けて入江富美子監督がメガホンをとったドキュメンタリー映画「天から見れば」の封切りに向けて、桜を描いた大作を制作中だ。
「これからも命をかけて、絵を描いていきたい。逃げ出したくなる時もあるけど、それを越えて自分にしか表現できない、思いをいっぱいこめた絵を描いていきたい。それでたくさんの人に喜んでもらえたら、本当に嬉しいんです」
2011/05/12 取材・文/花井奈穂子 写真/ 小田原大輔