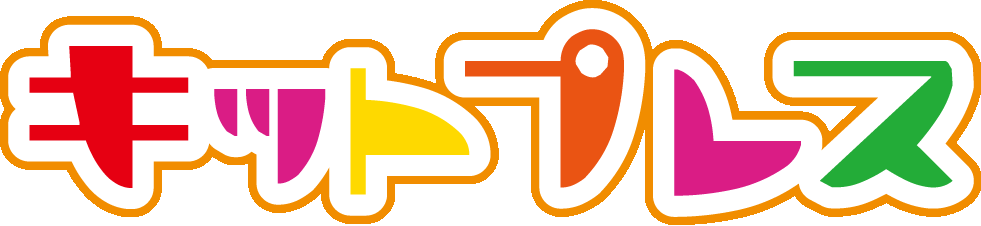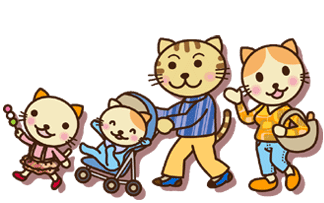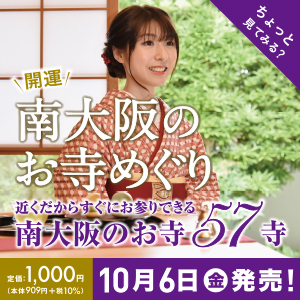クラシックをもっと身近なものに―そう願っていた夫の遺志を継いでいく

「ここを守っていきたいんです。クラシックをもっと身近で楽しいものに、とずっと願っていた稲本の遺志を私が継いでいきたいと思っています」
かつてクラリネット奏者の夫、耕一さんが毎月のようにライブを開いては、爆笑に包まれていた「堺テクネルーム」。
3年前に耕一さんを亡くしてからは、その細腕ひとつで運営を続け、歌声サロンを開催したり、ピアニストとなった長男・響さんやクラリネット奏者の次男・渡さんのコンサートを開いては、たくさんの人を楽しませてきた。
「ヨーロッパには日常の中にクラシックがある。日本でも気軽にランチを食べるようにクラシックを楽しめる…そんな社会を堺から発信したいといっていた稲本の想いをこの場所で次の世代につないでいく――それが私の使命かもしれません」
クラシックに革命を起こした夫の思い
彼女の弟もクラリネットを学んでいた縁で、知り合ったのが夫の耕一さん。
「彼はちょうどドイツ留学から帰ってきたところで、当時の堅苦しいクラシックのイメージを変えたいと思っていました。彼の話を聞けば聞くほど、音楽に対する真摯な思いがひしひしと伝わってきて。でね、プロポーズされた時、この人の音楽を支えたい!って心から思ったんです(笑)」
言葉どおり陰になり日向になり、いつも二人三脚で歩いてきた。
「日本人ならではの感性を大事にした、気軽に楽しめるクラシックがあるはずだ」という思いから、彼は数々の“革命”を起こしていく。
まず当時はあり得なかった、民謡とクラシックをコラボさせるという斬新な作戦。
それはクラシックも日本民謡も、ルーツは同じなのではないか…というユニークな発想からだった。「奈良時代にモンゴルから馬とともに遊牧民の音楽が入ってきて、それがいつか小諸馬子唄になり、江差追分に受け継がれていったらしいんです。一方でその音楽は西へも伝わって、ハンガリー民謡になった。クラシックはもともとハンガリー民謡が源流なのでルーツは一緒だと考えたんですね」
ならばと今度は日本民謡を取材するため、各地を飛び回るようになる。
「行けばその土地の人たちとお酒を酌みかわして、唄を歌って演奏して。地元にとけ込みながら民謡の心を学んでいったんです」
こうして江差、津軽、会津、武富島…民謡発祥の地をめぐり、様々な人と関わりながら独自の音楽を生み出していった。
そして初リサイタルでは、クラリネットで民謡を演奏。批判は覚悟の上だったが、意外にも評判は上々だった。
さらに翌年には、演奏の合間に気軽なおしゃべりを入れるという試みに挑戦する。
「当時はエンビ服姿で、黙ったまま演奏しておわり。それが稲本は観客を楽しませようと、曲のエピソードをしゃべるから盛り上がる。3年目には司会も入れて、託児所も作って…とクラシックコンサートを変えていったんですね」
また、ある視覚障がいのサポートをしている人との出会いから、民謡や日本の歌を演奏したCD「風を感じて…」も発売。目の不自由な子どもたちの心に、故郷の音色を残したいと、今もCD寄贈の活動を彼女が引き継いでいる。
夫婦ふたりで起ち上げたテクネルーム
「下駄ばきで気軽に、音楽や文化を楽しめる場所を」
そんな思いから28年前、自宅の一部を改築してオープンしたのが「堺テクネルーム」だ。風情たっぷりの町家を一歩入ると、現れるのは2台のピアノが置かれた異空間。テクネとは英語のテクニックの語源だが、古代ギリシャでは酒をかたむけながら皆で、哲学や文化をワイワイと談義することをそう呼んでいたのだとか。そんなリラックスした文化交流の場を、という思いでテクネと名づける。
ここで繰り広げられる耕一さんのパフォーマンスは、クラリネットを次々に分解しながら曲を吹いたりと、それはユニークなもの。
その一方でライブを盛り上げるのが彼女の役目だ。毎月違うテーマで、例えばフランス音楽の時にはワインソムリエを招いたり、ふるまうデザートを考えたり…とまさに夫唱婦随で歩いてきた。
だが耕一さんは咽頭がんのため3年前に他界。
「手術で声を失っても食道発声のリハビリを重ねて、最後の最期まで酸素吸入をしながら、病院のロビーでコンサートをやるような人でした」
彼の技術や音楽への想いは、ふたりの息子たちに引き継がれている。
特に次男の渡さんは今、堺を拠点に様々なアイデアを駆使して、クラシックをエンターテイメントにしたいと活動中だ。
そして夫が残したこのテクネルームは、彼女がその遺志を継いでいく。
「どこまで出来るかわからないけれど、みなさんに喜んでもらえるようなライブを企画していけたらなと思うんです。稲本への想いですか?ずっと尊敬していましたけれど、今はもっともっとその思いが深くなる一方です(笑)」
<2017/12/8 取材・文/花井奈穂子 写真/ 小田原大輔>