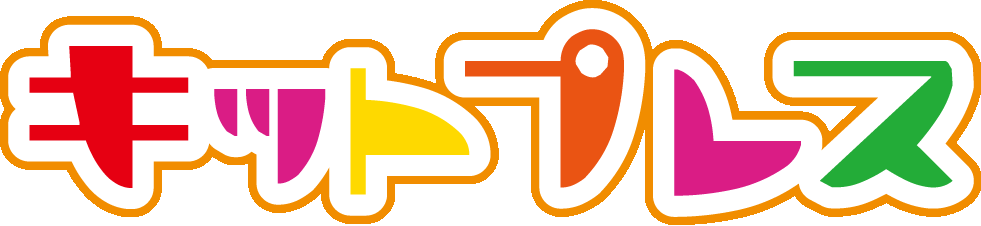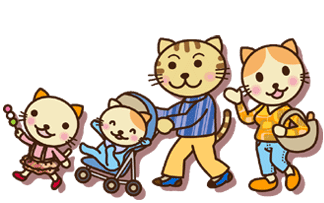若い世代も巻き込んで、写真業界をもっと盛りあげたい!

File.105
写真家 「Photostudio S」代表取締役
すぎたに まさひこ
杉谷 昌彦さん [大阪府堺市在住]
公式サイト: http://photostudios.jp/

1971年 堺市出身
2003年 写真家・テラウチマサト氏に師事 写真家ネームは杉谷岬二地(じゅにあ)
2009年 「株式会社 Photostudio S」設立
大阪を拠点にファッション広告、ブライダル等の撮影を手がける。「Google おみせフォト」の認定パートナーであるほか、写真教室「PHaT PHOTO」講師も務める
「僕らが“感性”って呼んでるものにも、実は理屈があるんですよ」
“感性”は選ばれた人だけが持つ、特別なもの。これがあると無いとじゃ大違い…と思い込んでいた。
だがこの“感性”、実はロジカルに解明できることが多いのだという。
「たとえば子どもが最高に楽しそうに遊んでる、そんな写真を撮るにはどうするか…子どもの足がね、宙に浮いてる瞬間を撮ればいいんですよ」
それだけで躍動感や子どもの幸福感が伝わって、人は心を揺さぶられる。
「理屈を知れば、簡単にオモシロい写真が撮れる。自分が何に感動して、それをどう伝えたいのかが見えてくる。そんな写真の楽しさを、若い人たちにドンドン伝えていきたい。それが低迷してる写真業界を変えていく、大きな一歩になると思うんです」
きっかけはNYで撮った写真
父は広告写真スタジオを営むカメラマン。幼い頃からすぐ手の届くところに、いつもカメラやフィルムがあった。
「だからといって写真に興味もなかったんです。中学の頃から新聞配達して、3年の時には“最高にリッチな中学生”目指してミナミでウェイターやってました(笑) それで高校になると、もう店を任されるぐらいまでいっちゃってて、スタッフの採用とかも僕が決めたりするわけです。そうなると、もう大学に行ってアイドリングみたいな時間過ごすのは、ムダな気がして…」
友だちより一足早く大人になってしまった彼は、社会人への近道として「大阪モード学園」に入ることを選ぶ。
「アートに興味があったので入学したんですけど、1年経つか経たないかで、ここにいる意味が見えなくなってしまったというか…」
ファッション、美容、映像、デザイン…様々なコースが用意されていたが、そのどれもが「結局アパレルやデザインの会社に勤める、就職してサラリーマンになる。それがここの最終目的やと気がついたんです。僕はサラリーマンになりたいわけじゃない、何かが違うって」
かなりの自由人だった彼は、同学園を1年で辞め、さまざまなアルバイトで日々を食いつなぐことになる。
本当に自分のやりたいことは何なのか――
道を探し続けていたある日、旅行先のニューヨークでふと手にしたカメラ。刺激的な街をファインダー越しにのぞいてみると、いいようのない楽しさがこみあげた。
「その時撮った写真が、我ながらスゴく面白かった!写真ってこんな楽しいもんなんやって、初めて気がついたっていうか… ウン、ここから写真の道にいくなって、なんかひらめいてしまったんですよ」
写真家・テラウチマサト氏との出会い
数年後写真家を目指し、父のアシスタントとして修業をしていた彼に、ひとつの転機が訪れる。
それが、多くの著名人や女優のポートレート撮影、イベントプロデュース等で、海外からも評価の高かった写真家・テラウチマサト氏との出会いだった。
独自の表現方法はもちろん、20代をターゲットにした写真誌の創刊、新人発掘を目指した参加型写真イベント「御苗場」のプロデュース…とマルチに才能を発揮している彼の、人となりに惚れこんだのだ。
さっそく彼の主宰する写真教室「PHaT PHOTO」に入学。
「ゼロから勉強し直しました。自己流でやってきたのとは大違い、知らんことばっかりでした」
その後テラウチ氏の専属アシスタントなどを経験し、2003年独立してフリーとなった彼は、杉谷岬二地(すぎたにじゅにあ)という写真家ネームで、ブライダル、ファッション、ポートレートとあらゆるジャンルの撮影をスタートさせる。
そして3年前には、自らの会社「Photostudio S」を設立。
さらに「Google」が運営する、ネット上で店内を360度パノラマで見られるというサービス「おみせフォト」の、日本でも数少ない認定パートナーにも選ばれる。
この先彼が目指すもの――そこには低空飛行を続ける写真業界を、自分の手でもっと盛り上げたい、というアツい思いがある。
「海外には自分の子どもの運動会に、専属のカメラマンを雇うのがあたり前のようなところだってある。それくらい写真が生活の一部になっているし、そのためにお金を払う。でも日本では絵画にはお金を払っても、写真を買おうという人は少ないでしょ。それが悔しいし、もっと文化的な価値を高めたいっていうのが僕の思いなんです」
そのためにも、もっと写真の魅力を伝えていきたいと、古巣である「PHaT PHOTO」の講師として、若い世代の育成にも力を注ぐ。
“感性”というあいまいなものを、科学的に、ロジカルに。上手く撮ることよりも、シャッターを押す感動を――
デジカメやスマートフォンの登場で、今や一億総カメラマンの時代。誰でも簡単に写真が撮れるし、ネットで公開することもできる。
「それでも、シャッターを押しただけでは撮れない写真がある。映らない景色がある。だから人を感動させる、自分を表現する、そんな写真を撮ってほしいんです」
<2013/10/04 取材・文/花井奈穂子 写真/ 小田原大輔>